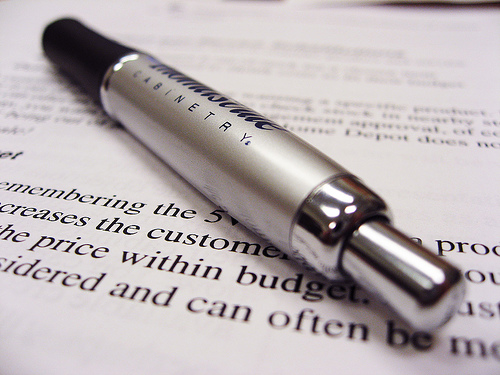
以前、クライアントさんから
「どうやったら上手くブログ記事が書けるのか」
という質問があったことを思い出したので、今日は少し趣向を変えて、文章術のお話をしたいと思います。
実際に書き始める前に、知っておくべきことを紹介していますので、是非実践してみてください。
目次
読みやすい文章とは?
まず、読みやすい文章の定義をしましょう。
大きく分けて、以下の8つが大切なことだと思います。
1. 適切な言葉遣いをしている
2. 構成がはっきりしている
3. 一文が完結
4. 一文一意
5. 読点の使い方が適切
6. いわゆる「うなぎ文」になっていない
7. 漢字の量が適切
8.話し言葉に近い
では、一つ一つ見ていきましょう。
1. 読みやすい文章は、適切な言葉遣いをしている
これは基本中の基本です。
文章を書き慣れていない人の大きな特徴の一つに
「変な思い込みや勘違いで言葉を使っている」
ということがあります。
たとえば、
× 『精錬された着こなし』
〇 『洗練された着こなし』
言葉を耳で覚えてしまった人に多い誤りですね。
意味はわかってもらえるかもしれませんが、こういうミスを頻繁にしていては説得力がなくなります。
上とは別に、間違いやすい日本語というのもあります。
× 『寸暇を惜しまず』
〇 『寸暇を惜しんで』
× 『汚名挽回』
〇 『名誉挽回』
のような言葉ですね。
こういう誤りを防ぐには、少しでも「あれ?」と思ったら調べる癖をつけることです。
ボキャブラリーの問題
ボキャブラリー(語彙)が多いかどうかも問われます。
というのも、日本語の文章は繰り返しを嫌う言語だからです。
同じ意味でも、別の表現を使えるかどうかで大きく違ってきます。
普段から意識しながら新聞を読むなり読書するなりして、少しずつ語彙を増やしてください。
2. 読みやすい文章は、構成がはっきりしている
学生の頃に国語の授業で習った『起承転結』のようなことです。
ここではビジネスブログに限った話をします。
読みやすい文章の構成の順番
『 結論 ⇒ 説明 ⇒ 補足説明 』
これを意識して書くと読まれます。
構成は見出しで作る
ブログ文章は基本的に流し読みされるとお考えください。
ユーザーはまずザッと見出しを読んで、自分が本当に読むべきものかどうかを判断します。
ですから、文章の構成を考えて見出しをつけます。
構成についてはこちらをご覧ください。
3. 読みやすい文章は、一文が簡潔
特に、説明文で長くなりがちです。
長くなったと思ったら、どこかで一度区切れないか考えてください。
読みやすい文章は主語と述語が近い
長い文章になると、主語と述語が離れがちです。
たとえば、こんな文章です。
『私はより多くの人に読んでもらえるような文章を書くために試行錯誤して見たが上手くできなかったので最終的に文章術の本を買った』
これを二つに分けて主語と述語を近づけると、
『私は文章術の本を買った。というのも、より多くの人に読んでもらえるような文章を書こうとして試行錯誤したが、上手くできなかったからだ』
となります。
読みやすい文章は不要な言葉が少ない
一度文章を書いてみてから、不要な言葉を削ってみましょう。
特に、接続詞はなくても意味が通じることが多いです。
4. 読みやすい文章は、一文一意
これは前項の『読みやすい文章は一文が簡潔』にも関係することです。
一つの文章では伝えたいことを一つにしましょうということです。
たとえば
『弊社では新規事業を来期中に立ち上げるべく計画を練っているところですが、それに付随する様々な問題を解決するために新たな部署を立ち上げ、既存事業にかけている人的リソースを極力減らさない方向で調整しようと考えています』
長いですね。
分けましょう。
『弊社では来期中に新規事業を立ち上げる計画を練っています。それに付随する様々な問題を解決するために新たな部署を立ち上げました。既存事業にかけている人的リソースを極力減らさない方向で調整するためです』
文脈次第では、もっと言葉を変えて簡潔にできると思いますが、単純に分けるとこんな感じになります。
5. 読みやすい文章は、読点の使い方が適切
最初の頃は読点『、』の打ち方で苦労されると思います。
ルールを決めておくと、迷うことがなくなります。
1. 主語の後
『私は、朝九時に出社した。』
2. 接続詞の後
『しかし、今日は祝日だった。』
3. 並列関係にある名詞の間
『山下、豊田、村重といった新入社員たちも当然いなかった。』
4. 並列関係にある文章の間
『私はタイムカードを押し、コーヒーを入れて机についた。』
5. 言葉の意味がわかるようにする
『こぼしたコーヒーが15万円のモニタと、キーボードにかかった』
この例で読点「、」がないとモニタもキーボードも両方15万円の価格だと勘違いされる可能性があります。
ちなみに、これに関してはそもそも言葉を変えたり、別の文に分けたりした方が良いこともあります。
迷ったときは上の基準に従い、それでもおかしいなと思ったときは、他の人が読みやすいかどうかを考えてください。
そもそも、なぜ句読点を打つかというと、読みやすくするためですから。
読点が多くなったせいで文章が『ぶつ切り』になっても読者が読みやすいのであれば、そちらを優先するべきです。
※あまりにぶつ切りになると逆に読みにくくなるので、気をつけてください。
6. 読みやすい文章は、いわゆる「うなぎ文」になっていない
飲食店にて
店員さん「ご注文はお決まりですか?」
Aさん「何にしようかな。うん、僕はカツ丼にするよ」
Bさん「僕はうなぎだ」
上記の表現で、店員さんは話の流れで「このお客さんはうな重(うな丼かも)を注文している」と理解します。
まさか、Bさんのことをウナギだとは思わないでしょう。
(ウナギという名字の方がいらっしゃるようですが、それにしてもこの流れで自己紹介はしませんよね)
こういう表現は日本語特有のものらしいですが、文章でこれをやってしまうと意味をとりにくいことがあります。
たとえば、こういう文章もそうですね。
『僕は昔、新大阪に住んでいた。今は梅田だ』
正しくは
『僕は昔、新大阪に住んでいた。今は梅田に住んでいる』
この程度ですと文脈でわかりますが、大阪の地理に詳しくない人が、「何が梅田なんだろう」と思ってもおかしくありません。
誤解されないように気をつけましょう。
7. 読みやすい文章は、漢字の量にも気を配っている
ビジネスブログを書くときの目安として全体の3割くらいが漢字になると良いと言われます。
これはあくまで目安ですから大体でいいと思います。
ですから、漢字が多いなと感じたら、普段は漢字で書くようなところでも、平仮名にしてみるのもいいかもしれません。
とはいえ、これも程度の問題です。
平仮名ばかりだと意味がとりにくくなることもありますので、お気をつけください。
8.読みやすい文章は、話し言葉に近い
これはつまり、平易な文章表現で書きなさいということです。
コピーライティングの世界では小学校5年生くらいの子供に読んで聞かせてわかるようなレベルにしなさいと教わります。
流し読みする人が多いので、一目で意味がとれるような文章にした方が読まれやすいということです。
無理して話し言葉に近づけることはありませんが、文章だからといって肩に力を入れて、わざわざ普段使わない堅い表現を取り入れる必要はないということですね。
まとめ
ご覧いただいてわかると思いますが、やはりここでもユーザー目線を忘れてはいけないということを書いています。
せっかく役に立つ情報、知っておいた方が良い知識を発信しているのに、読んでもらえないと読者のためにも自分のためにもなりません。
読まれる準備を十分にしてから、情報を発信するようにしてください。
役に立ったとき、気が向いたときに是非シェアしてください。
よろしくお願いします。

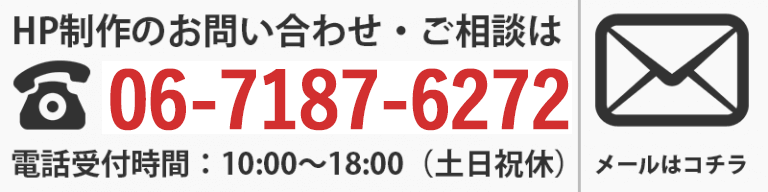
はじめまして^^
とても分かりやすく勉強になりました。
他の記事もぜひ読ませていただきます。
ありがとうございました。
Yuiさん、お読みいただき、ありがとうございます!(^^)
とても嬉しいです。
他の記事もごゆっくりお読みください。<(_ _)>